化粧品に配合される成分の基準とは|兵庫県尼崎市いしの行政書士事務所
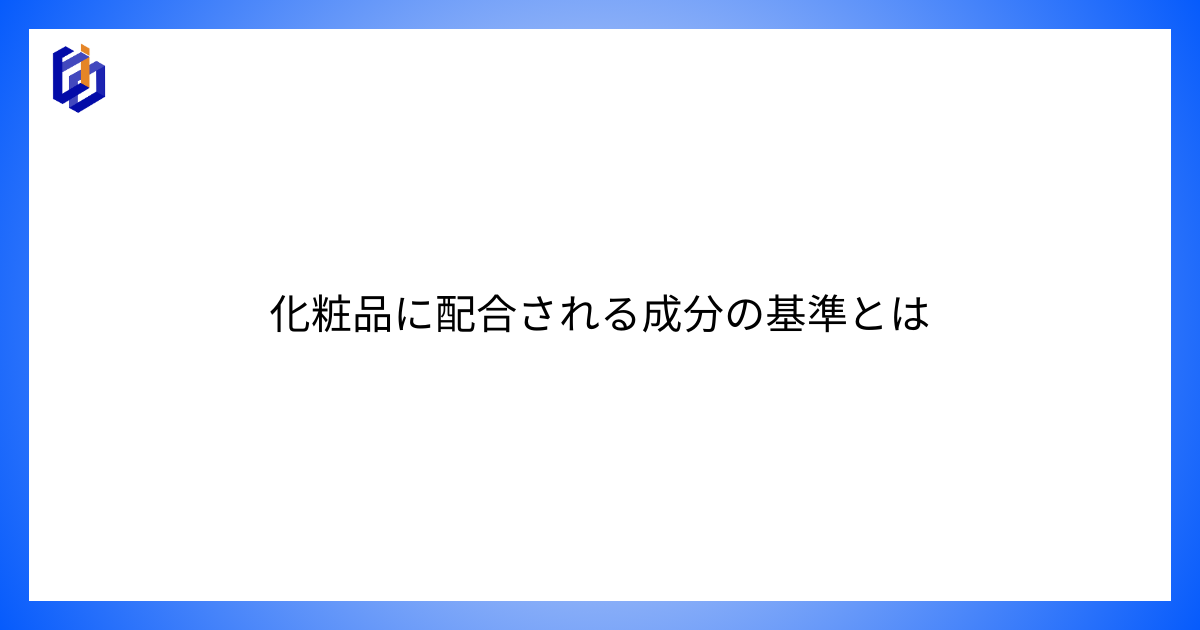
化粧品による健康被害を聞いたことはありますか?
石鹸の成分により多数の人にアレルギー反応が起きたことが過去に話題になりました。
化粧品は人に使用する物なので、どんな成分でも使えるという訳ではありません。保健衛生上の危害を防ぐために化粧品に使用できる成分には基準※が設けられています。基準を満たさない物は化粧品として販売できません。
基準の全体像は下表の通りです。
スクロールできます
| 備考 | ||
| 配合が禁止されているもの (ネガティブリスト) | 医薬品の成分 | 以下を除く ・添加剤として使用される成分 ・化粧品基準 「別表第2」、「別表第3」、「別表第4」に 記載の成分 |
| 「生物由来原材料基準」に適合しない物 | ||
| 第一種特定化学物質、 第二種特定化学物質、 厚生労働大臣が定めたもの | 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律 | |
| 化粧品基準「別表第1」に記載されている成分 | ||
| 防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素以外の成分の配合制限 (ネガティブリスト) | 化粧品基準「別表第2」 | 化粧品の種類や使用目的ごとに、100g中の最大配合量として制限 |
| 防腐剤、紫外線吸収剤、タール色素、 グリセリンの配合制限 (ポジティブリスト) | 化粧品基準「別表第3」、「別表第4」 | 化粧品の種類や使用目的ごとに、 100g中の最大配合量として制限 別表第3:防腐剤 別表第4:紫外線吸収剤 |
| タール色素 | 「医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令」第3条を準用 ※赤色219号、黄色204号: 毛髪又は爪のみに使用される化粧品に限り配合可 | |
| グリセリン | グリセリンの成分100g中、ジエチレングリコール0.1g以下であること。 |
※ 化粧品基準 平成12年9月29日 厚生労働省告示 第331号
化粧品基準は通知の発出により度々改正されています。最新情報を確認しておくことが必要です。
目次
配合成分の基準
使用できない成分
以下の成分は配合禁止です。
- 医薬品の成分 ※以下の場合に限り、配合できる。
- 添加物として使用される成分及び、化粧品基準の別表第2、第3、第4に掲げる成分
- 旧種別許可基準内の成分・分量のもの
- 平成13年3月31日までに化粧品としての承認を受けた成分・分量のもの
- 生物由来原料基準に適合しない物
- 第一種特定科学物質、第二種特定科学物質、厚生労働大臣が定めたもの
(化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律) - 化粧品基準 別表第1に記載されている成分
使用できるが、範囲が設けられているもの
- 化粧品基準 別表第2、第3、第4
- タール色素 医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令第3条を準用
- 赤色219号、黄色204号
- グリセリン
1. 化粧品基準 別表第2、第3、第4
化粧品の種類や使用目的ごとに制限(100g中の最大配合量などとして)が設けられています。
例)
・「チラム」という成分
石けん、シャンプー等の直ちに洗い流す化粧品では、100g中 最大で0.5gまで配合できる
・「サリチル酸オクチル」という成分
粘膜に使用されることがない化粧品のうち洗い流すもの では、100g中 最大で10gまで配合できる
基準が細かく規定されています。逸脱しないよう注意してください。
2. タール色素
医薬品等に使用することができるタール色素を定める省令第3条を準用。
ただし、赤色219号、黄色204号は毛髪又は爪のみに使用される化粧品に限り配合できます。
3. グリセリン
グリセリンの成分100g中、ジエチレングリコール0.1g以下であること。
企業責任が問われる
化粧品は法令上の要件を満たせば届出のみで販売が可能です。
厚生労働省による承認審査が不要な一方で、安全性などについては全て企業が責任を負います。
メーカーの管理体制が重要となります。
そのため販売、製造には許可制が取られています。
あわせて読みたい

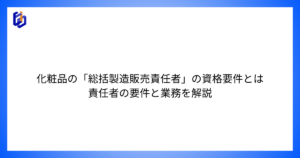
化粧品の「総括製造販売責任者」の資格要件とは|要件と業務を解説
化粧品のビジネスを始める人は「責任者」の人材確保を進めてください。「化粧品製造販売業許可」「化粧品製造業許可」には責任者の配置が必要だからです。 製造販売業 …
まとめ
化粧品の成分について解説しました。
- 配合できる成分は、化粧品基準により規定されている。
- 安全性はメーカーが責任を負うため管理体制が問われる。

